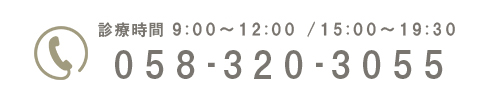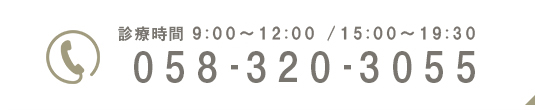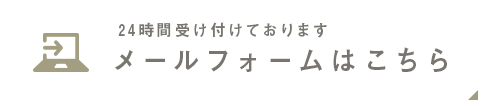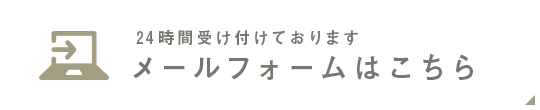出っ歯はほうれい線の原因になる?
2023.10.16更新
「出っ歯が気になる、治したい!」と考えている方なら、一度は歯科矯正を考えたことがあるはずです。しかし、歯科矯正をすると「若返った」なんて嬉しい噂もある中で、そんな情報とは裏腹に、歯科矯正をしたことでかえって「老けてしまった」なんて噂もあります。見た目を改善するはずが、思わぬ悩みが増えてまったなんてことにならないように、原因と対策を見ていきましょう。

ほうれい線ができる原因とは
女性なら特に気になるのが、年齢とともにできはじめる顔のシワ。その中でも特に悩みの種と言われているのが口元にできるほうれい線です。ほうれい線があるとないとでは、顔の印象がガラっと変わると言われているほど、見た目の印象を左右する部分にもなります。そもそも、ほうれい線はどんな原因でできてしまうのでしょうか。
加齢による頬のたるみ
年齢が上がるにつれて、目立ってくる顔のたるみ。頬を支えている肌のハリが衰えることで、重力に逆らえずに頬がしたに下がってしまいます。そうすることで、ほうれい線が気になるようになります。さらに、年齢や様々な理由から筋力が衰えることにより、ほうれい線が目立ちやすくなります。
特に、口元を囲うように覆っている「口輪筋」と口角からこめかみにかけて伸びる筋肉の「頬骨筋」といった表情筋がほうれい線に大きく作用しています。表情筋の衰えは、無表情の人や顔の筋肉をあまり使っていない人に起こりやすいです。
歯並びが悪い
歯並びが悪い人は、ほうれい線ができやすいケースがあります。特に、前歯が突出している、いわゆる「出っ歯」と言われる歯並びの人ほど、ほうれい線ができやすいと言われています。前歯の突出具合にもよりますが、前歯が唇からはみ出るようなタイプの人は、前歯を上唇で隠す癖がついている人も多く、肌にシワがつきやすくなってしまいます。
さらに、出っ歯が原因で無意識に口呼吸をしてしまい、それが癖になってしまうことで結果的に口周りの筋力低下の原因になり、ほうれい線をできやすくしてしまっている場合があります。
噛み合わせが悪い
出っ歯などで噛み合わせが悪い状態が続くと、左右どちらかに強く負担がかかりすぎてしまうなどで顎が歪んで変形してしまい、ほうれい線が目立ちやすくなってしまうことがあります。
また、筋肉が常に緊張状態になってしまうことで、シワを強調してしまったり、長時間筋肉を収縮させてしまうことでほうれい線の原因になってしまいます。しかし、必ずしも噛み合わせが良い人でもほうれい線ができない訳ではありません。
歯科矯正での変化は?
歯並びがシワの原因になることは分かりましたが、歯並びを改善する為に行う歯科矯正は、ほうれい線にどのような影響を与えるのでしょうか。

目立たなくなるパターン
まずは、歯並びを気にしていたことで表情筋を普段からあまり使っていなかった人が、表情に自信を持つことでたくさん笑えるようになり、表情筋が鍛えられることで改善していくことがあります。コンプレックスが改善されることで、自分に自信がもてて表情も明るくなれたら素敵ですよね。
また、元々口元が突出していた場合、口と頬の境界線が目立ちやすく、それがまるでほうれい線のように見えてしまっていた人が、出っ歯を矯正することでほうれい線が目立たなくなることがあります。
ただし、これらは直接的に矯正治療が大きく改善に関わった、というよりは間接的に改善していると捉えた方が良いでしょう。
目立ちやすくなるパターン
もともと、口元の突出が少ないのにも関わらず抜歯を行い、口唇を下げすぎてしまった場合に「ほうれい線が目立ちやすくなった」「老け顔になった」と感じることがあります。
もしくは、前歯が突出していたことが改善したことにより、唇に遊びができそれが原因で引っ張られていた皮膚にたるみが生じることで、ほうれい線が目立つようになったと感じる方もいるようです。
しかし、これらも仮説に過ぎず、抜歯を行ったからといって必ずほうれい線ができるあるいは目立ちやすくなるということはありません。
ほうれい線を予防する為には
そもそも歯科矯正は、「歯並びを改善するもの」なので、きれいな歯並びになり口元の印象が変わったり、歯並びが良くなって歯磨きがしやすくなることで虫歯予防になる、などの本来の治療目的があります。
歯科矯正でほうれい線が大きく変化したり、完全に消えるということは基本的には少ないです。そこで、ほうれい線に悩む方に歯科矯正以外の具体的な改善方法をご紹介します。
専門の医師に診断してもらう
矯正を行う前に、必ず医師に横顔の状態なども診断してもらい適切な状態をゴールにすることで、歯科矯正でのシワの原因を防ぐことができます。適切な治療計画に沿って、治療を行うことが大切です。
また、必ずしも歯並びが原因でないことも考えられますので、美容皮膚科などに相談して、皮膚専門の医師に診てもらうことも悩みの改善につながります。
左右両方の歯でバランスよく噛む
どちらかだけの歯で噛んで食事をすることが癖になってしまうと、顔の左右の筋肉に差が出てしまうことで、顔に歪みが生じてしまいます。片側噛みする方の筋肉だけピンと張ってしまうことで、ほうれい線の濃さなども見た目で違いが生まれてきます。癖になってしまうと長期間この状態が続いてしまうので、食事をする際は、両側で均等に噛むことを心がけましょう。
表情筋を鍛えるエクササイズをする
筋力の低下によって、たるみが生じ、結果的にほうれい線の原因になってしまうので、普段から表情筋を鍛えるエクササイズをすることで、筋力の低下を予防することができます。硬いものを噛んだり、ガムを噛むことも効果的です。重力に負けないように、普段から表情筋のケアをすることが大切です。
保湿する
乾燥もシワの原因の一つです。加齢により、肌の水分量が少なくなってしまうので普段から保湿することを心がけましょう。
保湿をすることで肌のたるみの予防や、ほうれい線がくっきりついてしまうことを予防できます。
紫外線対策をする
特に一番大切だと言っても過言ではないのが、紫外線対策です。ほうれい線の原因となる顔のたるみは、紫外線による光老化で加速します。普段から、外出時だけでなく家にいる時もUVクリームを顔に塗ったり、外出する際は、日焼け止めを必ず塗る、日傘を使用する、帽子をかぶるなどのケアが大切です。
投稿者: