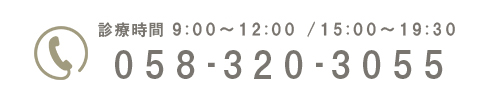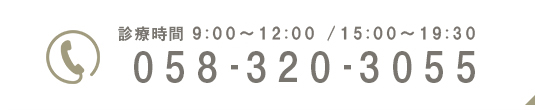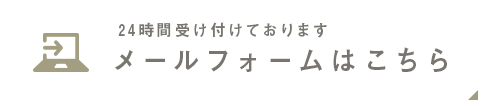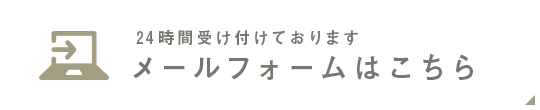ほうれい線と歯並びは関係がある?
2024.04.25更新

ほうれい線は、歯並びと直接的な関係はありません。しかし、中には歯並びや噛み合わせの問題によって、年齢に関わらずほうれい線が目立ってしまうことがあります。
例えば、噛み合わせが悪い重度の出っ歯や受け口などの不正咬合の場合、咀嚼がうまくできないことから、食事の際に十分に噛まない癖が定着してしまいがちです。
咀嚼をあまりしないことで、頬骨に繋がっている咬筋が衰え、頬のたるみやほうれい線が強調される可能性があるとされています。 また、ほとんどの不正咬合で見られる口呼吸もほうれい線に繋がることがあります。口を開けた状態での呼吸が続くと、唇を閉じる時に働く「口輪筋(こうりんきん)」という筋肉が衰えてしまいます。口輪筋は、頬筋などの表情筋と繋がっている重要な筋肉です。この口輪筋が衰えることで、皮膚がたるんでほうれい線が目立ったり、口角が下がったりするリスクがあるのです。
ほうれい線が目立ちやすい歯並び
噛み合わせに関係なく、ほうれい線が目立ちやすいとされている歯並びは、主に上の前歯が前方に突出している重度の出っ歯(上顎前突)と、上下の歯が前方に突出している口ゴボ(上下顎前突)です。
出っ歯や口ゴボは、上顎の歯列が前方に突き出ています。これにより、鼻の下である人中から上唇が皮膚ごと前に押し出されるため、境目となるシワが強調されてほうれい線が目立ちやすくなるのです。
ほうれい線は加齢や生活習慣によっても深くなりますが、出っ歯や口ゴボのような、ほうれい線付近の脂肪や皮膚などの組織に影響を与える歯並びの場合、それがより目立つ可能性があります。
歯列矯正でほうれい線が改善される?
歯列矯正がほうれい線の改善に効果があるかどうかについては、明確な科学的根拠はありません。ほうれい線の形成は、歯並びだけでなく、顔の筋肉の使い方や皮膚の老化など、さまざまな要因によって引き起こされるためです。
ただ、顔のバランスや筋肉の使い方に悪影響を与える不正咬合の場合、歯列矯正によって噛み合わせや歯列を改善することで、ほうれい線の見た目に一定の改善が見られることがあります。これは、表情筋や咀嚼筋などの顔の筋肉が、治療によって正常に機能するようになるためです。
前者の表情筋は、笑顔や口角を上げるなどの動作に使われる筋肉です。表情筋が使われていないと、顔の皮膚が引き締まりにくくなり、特に目元のシワや口元のほうれい線が目立ちやすくなります。
一方、咀嚼筋は主に食べ物を咀嚼する際に使われる筋肉です。この咀嚼筋が衰えることによって頬がたるみやすくなり、ほうれい線の原因になることがあります。
矯正治療は歯列を綺麗に並べた上で、しっかりと噛むことができるようにする治療です。よって、治療後は歯並びが良くなったことで笑顔が増えたり、噛み合わせの改善で食べ物をしっかり噛むことができたりすることも多いため、上記の表情筋や咀嚼筋が適切に働くようになることがあります。
つまり、矯正治療によって顔の筋肉が正常に機能することで、ほうれい線の目立ちやすさが軽減されるケースもあるということです。
しかし、ほうれい線の改善には個人差があり、歯列矯正が直接的な効果を持つわけではありません。いずれにしろ、「矯正治療でほうれい線が消えたり、劇的に改善されたりしない」ということは頭に入れておきましょう。
ほうれい線の改善を目的として歯列矯正を考えている場合には、矯正治療だけでなく、皮膚のケアや美容整形なども一緒に検討することをおすすめします。
ほうれい線を第一に治したいと考えている方に最も重要なのは、自身の状態や希望に合った治療法を専門家と相談し、適切な方法を見つけることです。
反対に矯正治療でほうれい線が濃くなることは?
一般的に、矯正治療によってほうれい線が濃くなるということはありません。歯列矯正は、主に歯並びや噛み合わせの改善を行う治療であり、ほうれい線に直接的な影響を及ぼすものではないためです。
ただし、治療方法によっては治療前よりもほうれい線が目立つように見えるケースもあります。
例えば、前歯を下げる必要のない方が抜歯矯正をした場合、歯を後退させすぎてしまうことで口元が過度に引っ込み、老けた印象になることがあるのです。ただ、治療前の適切な治療計画によってこのリスクは回避できるため、抜歯矯正だからと言って必ずしも起こることではありません。
また、まれにですが突出していた上の前歯を正常な位置に下げると、これまであまり目立っていなかったほうれい線がはっきりとするケースもあります。しかし、この場合は口元の出っ張りにより目立ちにくかったほうれい線が、出っ歯を解消したことで本来の姿に戻っただけと考えられるため、矯正治療によって形成されたとは言えません。 このように、歯列矯正は通常ほうれい線に直接的な影響を与えるものではないものの、治療方法や個人の状況によって口元の見た目が変わることがあります。よって、矯正治療をする際には、適切な治療計画と矯正医のアドバイスを受けることが大切です。
投稿者: