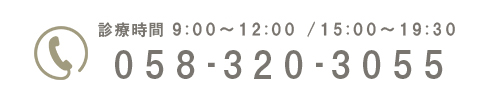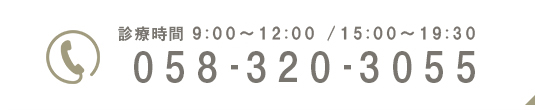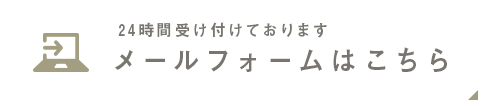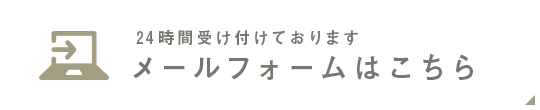八重歯は部分矯正できる?
2024.01.22更新

八重歯があるとチャームポイントにもなるので、ネガティブなイメージを持つ方は多くないでしょう。
しかし、八重歯は愛嬌があるイメージを与える反面、むし歯や歯周病のリスクが高くなってしまいます。
八重歯の部分矯正ができるケース
八重歯の部分矯正は誰でもできるわけではありません。ここでは、部分矯正ができるケースをご紹介します。
八重歯以外の歯並びに問題がない
八重歯に限らず部分矯正は、歯並びに問題がない場合にしか行えません。そもそも八重歯はスペースがないところに生えてきてしまった犬歯で、ねじれたり重なったりして生えてきます。
少しのねじれや重なりであれば部分矯正が可能なことがありますが、重度の場合は部分矯正できません。
ガタガタが重度だったり歯列が出っ歯だったりする方も、部分矯正後に後戻りする可能性があるため施術できないでしょう。
歯並びに問題がある方が八重歯を部分矯正すると、後戻りしやすいだけでなく健康な歯に力が加わりすぎてしまうことがあります。
歯が移動するスペースを作れる
部分矯正の場合、歯列拡大ができなかったり抜歯を行えなかったりするので、歯を移動するスペースがないといけません。
歯にヤスリをかけてスキマを作るIPRは、1つの歯間につき0.5mmまでしか削れないといわれています。親知らず・奥歯を除いた歯列の全歯間をIPRで0.5mmずつ削ると、片顎5.5mmとなるでしょう。
そのため、八重歯を5.5mm以上移動させなければいけないケースでは、部分矯正を断られる可能性が高いです。
部分矯正でも抜歯をすることはありますが、状態によっては抜歯する選択肢が選べません。抜歯することでスペースが確保されるものの、抜いたことでスペースが余ってしまい、すきっ歯になる可能性があるからです。
前歯の噛み合わせが深くなっていない
上の歯が下の歯に2mmほど重なっているくらいの深さが正常な噛み合わせです。噛み合わせが悪く下の歯が見えない過蓋咬合の状態では部分矯正ができません。
これは、顎の骨格バランスに問題があることが多く、部分矯正では改善できないためです。また、過蓋咬合の場合、部分矯正したとしても後戻りする可能性が高くなります。
後戻り防止のための器具もありますが、噛み合わせが深いと装着できません。
前歯の噛み合わせが深い場合以外でも、不正咬合の方は軽度であれば部分矯正できますが、重度の場合は全体矯正になることが多いと覚えておきましょう。
八重歯を矯正するメリット
むし歯や歯周病を予防できる
八重歯は隣接する歯と重なっているため、隣の歯が後退している状態です。そのため、歯ブラシやデンタルフロスでは汚れが落しきれず蓄積してしまいます。
食べカスを放置してしまうと細菌が増え、むし歯や歯周病が進行します。また、八重歯が生えている方の多くが口が閉じられないために、口呼吸になりがちです。
口呼吸は唾液が乾いてしまい、細菌が繁殖しやすい状態になります。これもむし歯や歯周病の原因です。
むし歯や歯周病は治療せずにいると、全身に細菌が回ったり顎の骨が腐ったりと進行するほど症状が深刻になっていきます。
そのため、むし歯や歯周病のリスクを減らすためにも、八重歯を矯正して正常な歯並びにしましょう。
正常な歯並びにすれば、適切なブラッシングやフロッシングによる日々のケアで歯の磨き残しが少なくなります。
口内の傷や口内炎が減少する可能性がある
八重歯がある方は、歯が口の外側に突き出ている状態です。そのため、突き出た部分が唇の内側を傷つけてしまい口内炎が発生しやすくなります。
また、歯が正常な位置から外れ、口の粘膜を継続的に刺激すると稀に口腔ガンの原因となることもあるので注意しなければなりません。
八重歯があって口内炎ができやすいと感じている方は、ガンのリスクを下げるためにも矯正治療を検討しましょう。
口内の傷や口内炎ができやすいと、食事をすることが億劫になり栄養不足に陥ってしまいます。こうなると、口内炎は治癒するまでに時間がかかるといった悪循環になりかねません。
食事の仕方に気を遣っていても、根本から治療しなければ解決できません。口内炎のストレスから解放されるためにも、八重歯の治療を行うことがおすすめです。
コンプレックスを解消できる
八重歯はチャームポイントではなく、コンプレックスの1つと思っている方も多いでしょう。
健康志向が強まった現在では、噛み合わせや口内炎などの解消だけでなく、見た目の悪さを感じる方が増えてきました。
「八重歯があることで歯を出して笑えない」と悩んでいる方だけでなく、顔つきに悩む方も多いです。
八重歯は歯の配置よりも外側に突き出ているため、この部分の頬が外側に膨らんでしまいます。口の端の頬が膨らむことで、顔の外観が小動物のように見えることもあるでしょう。
八重歯を治療することで、歯を見せやすくなる・笑顔に抵抗がなくなる・顔の輪郭が変化するといった効果があります。これによってコンプレックスの解消につながるでしょう。
噛み合わせが改善できる
そもそも犬歯は噛み合わせをサポートして、歯列にかかる圧力を分散させる役割があります。
しかし、八重歯があると上下の犬歯が噛み合わず、他の歯に大きな負担がかかって歯の寿命を縮めてしまいます。
噛み合わせが悪いとむし歯・歯周病・知覚過敏・顎関節症などのリスクがあるため、改善することを検討しましょう。
八重歯による噛み合わせを改善すると、食事をしっかり噛めるため、消化がよくなることで胃への負担も軽減されます。ただし、八重歯での噛み合わせ改善は一部しかできません。
顎の骨格バランスや出っ歯など全体的に歯列矯正をしなければならないケースでは、部分矯正による噛み合わせ改善ができないのです。
この判断は素人ではできないので、歯科医師に相談して部分矯正か全体矯正かを見極めてもらいましょう。
投稿者: